|
|
| 第39号2014年6月発行分 | 第41号2016年7月発行分 |
|
| 「人は死ぬために生きている⁉」 |
|
1 父(前住職)の遺言 4月29日に父(前住職)が亡くなり、火葬までの数日間、「最後のお別れに」「最後にひと目お顔を」と多くの方が弔問に訪れて下さいました。 小学校・中学校・高校と同級であったその方は、遺骸との対面の後、生前の父とのある「思い出」を語って下さいました。 「昔、○○ちゃん(父の愛称)に 『人間は何のために生きとるのかな?』 と尋ねたことがあったんだが、そうしたら○○ちゃん、 『死ぬために生きとる!』 と答えてなあ。ずいぶんびっくりしたんだが、○○ちゃん、どういうつもりでああいうことを言ったんだろうか?」 この会話がいつ頃交わされたものかはわかりませんが、「死ぬために生きている」とは我が父ながら結構乱暴な、というか大胆な物言いをしたものです。 「どれだけ頑張っても結局は死ぬんだから、何をしても無駄だ。 「あいつがそんな意味で言うはずはない。と思いながらも、 「じゃあ、どういう意味だろうか?」とずっと疑問に思っていらしたのではないでしょうか。 父の本意は不明ながら、私は次のように答えさせていただきました。 「『死ぬため』の前に『よく』をつけてみたらどうでしょう。 この答えにその方は「なるほど」と頷いておられました。 「生き切る」「死に切る」の反対語は何でしょうか。 自分の人生の最期に何らかの心残りややり残し、未練や後悔が残ってしまった時、人はこう言うのではないでしょうか。 「死んでも死に切れない!」 この世に恨みを残し、死んでも死に切れなかった人間はどうなるのか。 怪談話はさておき、古代インド以来、この世で煩悩(ぼんのう)にまみれた人間は、次の生では良くないところ(悪道・悪趣)に生まれ変わると考えられていました。 貪欲(とんよく)―絶えず欲求不満で貪りの心に執われて生きた人は、折角手に入れた食べ物も燃え上がり常に飢えていなければならない餓鬼(がき) |
|
.jpg) |
|
| 【「六道絵・阿修羅道図」(聖衆来迎寺蔵)】 | |
3 「涅槃」(完全燃焼) これに対して釈尊、お釈迦様の目指されたものが「涅槃」(ねはん)―輪廻を断ち切った、二度と流転することがない境地でした。 「涅槃」の原語「ニルヴァーナ」は「吹き消す」という意味であり、「涅槃」とはつまり「(流転の原因である煩悩の)火を吹き消された状態」を指しますが、金子大榮先生はそれをさらに積極的に 「涅槃とは完全燃焼である」とされ、 「煩悩妄念の自らを薪として自らの生涯を『完全燃焼』たる涅槃へと一歩一歩向かわしめるものが親鸞聖人が説かれた本願念仏の仏道である」と説かれました。 |
|
.jpg) |
|
| 【「釈迦涅槃図」(一畑薬師・一畑寺蔵)】 | |
4 誰かと較べる必要はない 私はそれを、自分は自分の与えられたこの「場所」で、他でもないこの「自分」を精一杯燃やして生きていくのだ、という「覚悟」であると考えます。 10年ほど前のベストセラーに『置かれた場所で咲きなさい』(渡辺和子著、幻冬舎・2012年) 花は置かれる場所・環境を自分では決められません。 風に吹かれるタンポポの綿毛は落ちる場所を選べません。 肥沃な土地に落ちることができれば幸運ですが、道端の砂利の上やひどい場合にはアスファルトの割れ目に落ちることさえあります。 そしてまた花は、「自分は別の種類の花の方が良かった」という愚痴や不平は零しません。 どの花もただ黙って、置かれた場所で、咲くべき季節に、その花ならではの色・形で、それぞれに精一杯咲いて散っていきます。 |
|
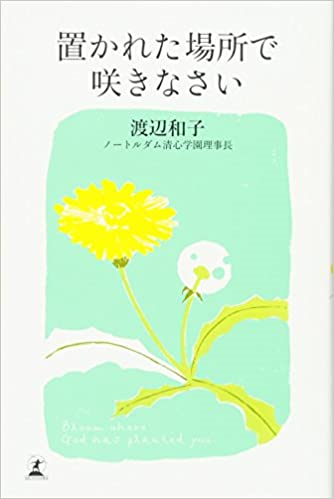 |
|
| 【渡辺和子著『置かれた場所で咲きなさい』】 | |
人間もそうあるべきではないでしょうか。 どれだけ転職や転居を繰り返して外的な環境を変えても、100パーセント満足のいく職場や居住地などどこにもありません。 どんなに自分が嫌いであっても自分が自分であること(男性であること、日本人であること、令和の時代を生きていること……etc)から逃げることはできないのです。 それならば、いたずらに他と比較して他人を羨むのでも、自分を貶めるのでもなく、今この場所で、この自分を咲かそうと精一杯生きる。 それ以外に、自分を燃やし尽くしていける道はないのではないでしょうか。 『大無量寿経』にははからずも次のように説かれています。 「如来(=釈迦如来)、世に出興したまう所以(ゆえん)は、群萌を拯(すく)い恵むに真実の利を以てせんと欲(おぼ)してなり。」(『大無量寿経』)私たち人間は「群萌」(ぐんもう)―群がり萌(きざ)す名もなき雑草一本一本―のような存在であり、お釈迦様が世に出られたのはこのような私たちをこそ救うためである、と。 この場合私たちは「花」ではなく「雑草」になるわけですが、親鸞聖人は『尊号真像銘文』の中でこの文を解説して 「仏(=釈迦仏)の世にいでたまうゆえは、弥陀の御ちかいをときてよろずの衆生をたすけすくわんとおぼしめすとしるべし」(『尊号真像銘文』)と述べて「群萌」を「よろずの『衆生』(しゅじょう)」と抑え、さらに別の箇所では、 「『十方衆生』というは、十方のよろずの衆生なり。として群萌=衆生=私たちである、と抑えていらっしゃいます。 「衆生」とは、人間を含んだあらゆる生きとし生けるものを表す仏教語ですが、『浄土論註』には、 「汎(ひろ)く衆生の名義を解するに、それ三有(さんう=三界)に輪転して衆多(あまた)の生死を受けるをもってのゆえに、衆生と名づく」(『浄土論註』)とあって、「慢」(まん)―他人と比較して自分を高みに置こうとする心―に基づいて貪欲・瞋恚・愚痴の煩悩を起こし、その結果三界註(さんがい、欲界・色界・無色界)、それも主に悪道・悪趣を延々と生まれ変わり死に変わり流転輪廻し続ける私たちのことである、とされています。 これが仏様の智慧の眼から見た私たちの「在り様」なのです。 そのような私たちに対して、煩悩に振り回されて流転輪廻を続けるのではなく、煩悩の身(命)を生きながらその身(命)を完全に燃焼させるべく、 「他人と自分を較べる必要はない。 お前はお前の道を歩くのだ。 と呼びかけてくださっているのが阿弥陀様であり、お釈迦様であり、親鸞聖人なのではないでしょうか。
|
|
 |
|
| 【融通念仏宗・専念寺「今日の法語」より】 | |
父が遺してくれた「死ぬために生きる」という言葉。 父がどんなつもりでそれを発したのか、本当のところはわかりませんが、現在の私はこの言葉をこのような教言―仏様からの呼びかけ―として受け止めています。 |
|
【註】 三界(さんがい) 仏教の世界観で、生きとし生けるものが生死流転(るてん)する、苦しみ多き迷いの生存領域を、(1)欲界(よくかい)、(2)色界(しきかい)、(3)無色界(むしきかい)の3種に分類したものをいう。 (『小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)』) |
|
| (『西念寺だより 専修』第48号に掲載) | |
| 《参考ウェブサイト》 Wikipedia「三界」の項 「生活の中の仏教用語・三界」(大谷大学・読むページ) 「聖衆来迎寺蔵『国宝・六道絵』を拝観して(大津市歴史博物館)」(山歩き町歩き日記) |
|
Copyright(C) 2001.Sainenji All Rights Reserved.